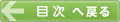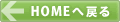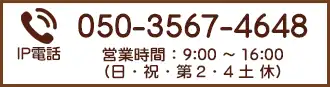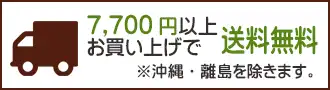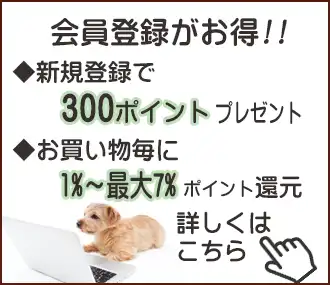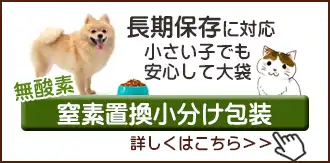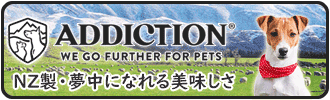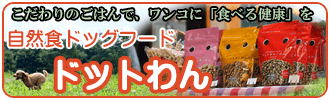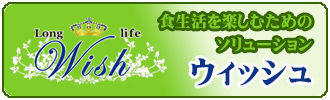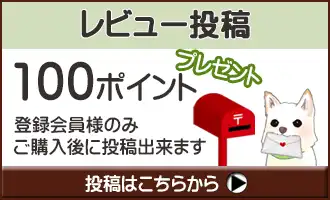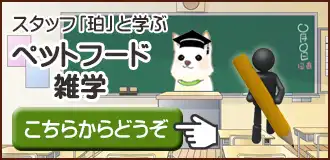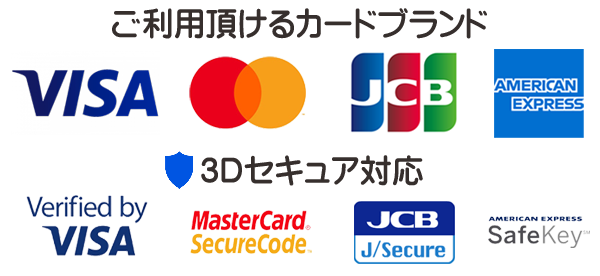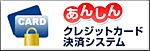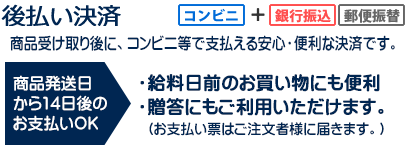メルマガ・バックナンバー
人の健康とペットとの関係、他
蝉の鳴き声が響き渡りますね。夏を感じさせます。この夏の愛犬・愛猫とのお出かけのご予定はいかがでしょうか?最近はペット同伴で入れる施設が増えてきました。ペットと一緒のお出かけを特集した雑誌も普通にコンビニで売られたりしています。1冊買っておくと何かと便利ですよ。
先月26日に出席してきましたインターペット・ビジネス・フォーラムの内容紹介の続きです。
*****************************
目次
1.国内犬と猫の飼育状況の推移
2.人の健康とペット
3.人とペットの高齢化への対応
4.災害とペットの救護
*****************************
1.国内犬と猫の飼育状況の推移
近年は猫ブームが到来しているのは山田様もご存じだと思います。ペットとして飼われている犬はここ5年間毎年約5%ずつ減少しています。では、猫はというとほぼ横ばいです。今年ペットの猫の数が犬を上回ることが予想されています。
今後ペットを飼いたいと考えている人の割合も犬は2011年に33%以上ありましたが年々減少しています。猫は約17%で横ばいです。前回も紹介しました「モフモフ」に触れたときに出る幸せホルモン「オキシトシン」は、猫の方が多く出るとの研究結果もあります。そのためかもしれませんね。人はペットに癒やしを求めているのかもしれません。
犬や猫を飼っている人に「生活の喜びを与えるもの」に関してアンケート調査した結果がペットフード協会にはあります。
犬の飼い主→1位:家族 2位:ペット 3位:趣味
猫の飼い主→1位:ペット 2位:家族 3位:趣味
○○様はいかがですか?店長の家は当然スタッフ犬「珀」が我が家の幸せを運んできています。
飼い主の年代別で見ると犬も猫も50代がもっとも飼育率が高く、若年層や60代以降は飼育率が低くなります。年齢と共にペットを飼う人の割合は増えるのですが、60代以降になると急に下がります。高齢になると「面倒を見切れない」「自分の方が先に・・」などの心配が出てくるためだそうです。でも、前回も紹介しましたように、ペットと飼い主の相互健康依存の関係があります。本当は高齢者ほどペットを飼いたいと願う人が多くなるはずです。このあたりは、3番目の話題で触れたいと思います。
ペットの平均年齢は、医学の進歩、食生活の向上と共に年々延びています。2011年と2015年を比較すると平均寿命は犬で13.85歳→14.85歳、猫で14.39歳→15.75歳となっています。ペットにも高齢化社会が到来しているといえます。
*****************************
2.人の健康とペット
1985年における外国の研究結果でペット飼育による国の年間医療費抑制額が試算されています。ドイツでは7,547億円、オーストラリアでは3,088億円もペットによって医療費が抑制されたとされています。
高齢者の年間の通院回数の統計では、犬を飼っている人は年間8.62回、飼っていない人は10.37回です。健康寿命(寝たきりにならずに生活できる年齢)は男性で0.44歳、女性で2.79歳もペット飼育の有無で差があるそうです。
社会福祉を考える上で、ペットを飼うことの重要性が問題になるのでは?ともいわれています。外国の研究試算のようにペットが医療費を抑えることが国内の研究でも明確にされると国もペット飼育を斡旋するようになるかもしれませんね。でも、健康という自分の利益だけを目的としてペットを飼う人が増えてしまうかもしれません。別の問題が起きないかな?と思うのは気のせいでしょうか。
家族としてかわいがり、愛犬や愛猫からも愛情を返してくれる。山田様も私もそんな思いで一緒に暮らしていると思います。当店のお客様は皆、そのような方ばかりです。
*****************************
3.人とペットの高齢化への対応
高齢者ほど本当はペットを飼いたいと願っていらっしゃる方がたくさんいますが、散歩など体力の問題やペットの方が長生きした場合を心配して躊躇する傾向にあるとのことでした。年齢により飼えなくなった場合のサポート体制は未整備なのが現実です。今後、このようなサポートサービスが広まるかもしれません。
人間の介護施設でペット同伴が可能な施設もまだまだ少ないです。人が介護施設に入る場合ペットと別れなければならず、介護施設への入居を拒否される高齢者もいらっしゃるとのことでした。
また、ペットの方の高齢化に着目すると人間には介護サービスは国の施策としても存在していますが、ペットの介護士を探そうとしても近所ではペット介護の専門家を見つけられないのが現状ではないでしょうか。パネリストの一人に「ペットケアステーション大阪」の代表者がいらっしゃいました。この団体では、ペットの介護のあり方や介護士育成・普及に力を入れているそうです。詳しくはサイトをご覧下さい。
http://petcare-station.com/
その方がペット介護の一例をご紹介下さいました。寝たきりの犬の場合、昔は誤嚥が怖かったので体を起こして食べさせていたそうですが、最近では寝たままの方が食べさせやすいとのことでした。とにかく食べさせないと衰弱するだけです。噛むこともままならないのでウエットフードを食べさせます。そのときにスプーンを使うとへこみにフードが張り付いて上手に食べさせられないそうです。この団体では寝たきりのわんちゃんに食べさせるときには「バターナイフ」を使うそうです。
*****************************
4.災害とペットの救護
先の熊本地震では環境省は初めからペット救護対応のために現地入りしたそうです。そのとき、「人間さえも大変なときにペットなんて」と心ない非難をさんざん浴びせられたとパネリストの一人環境省の方がおっしゃっていました。
ですが、被災ペットを救護しないとその飼い主である被災者の救護が出来なくなることは東北の震災でも栃木の洪水(自衛隊ヘリが飼い犬も含めてピックアップした話は有名ですね)でも証明されています。そのため、非難は承知で現地入りしたとのことでした。
ペット嫌いや動物に対するアレルギーというのも一つの価値観や生理的な問題です。ペットを家族と見ている人とこれらの人で共存できるようにするにはどうするか?多様な価値観の人たちが互いに尊重し合うことが解決の前提になります。
今後予想される首都直下地震や南海トラフ震災では熊本のような行政の対応は無理、とのことでした。被害が大きすぎます。(南海トラフでは関東から九州までの広範囲で先の東北震災のような被害が発生すると予想されています)
日頃から、飼い主はワクチン接種やしつけ、クレートトレーニングなど適正な備えをしておかないと、ペット同伴が可能な避難所が作られても対応が出来なくなるそうです。飼い主側も考えていかなければならない問題です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
ここで紹介していない内容を含めて写真付きでFacebookで紹介しています。
こちらも是非ご一読下さい。
https://www.facebook.com/pet.dining/
ここに掲載の内容はあくまでご参考いただくことを目的としております。この内容に基づくあらゆる行動の結果について当店は責任を負いかねますことをご了承ください。